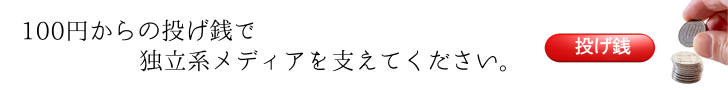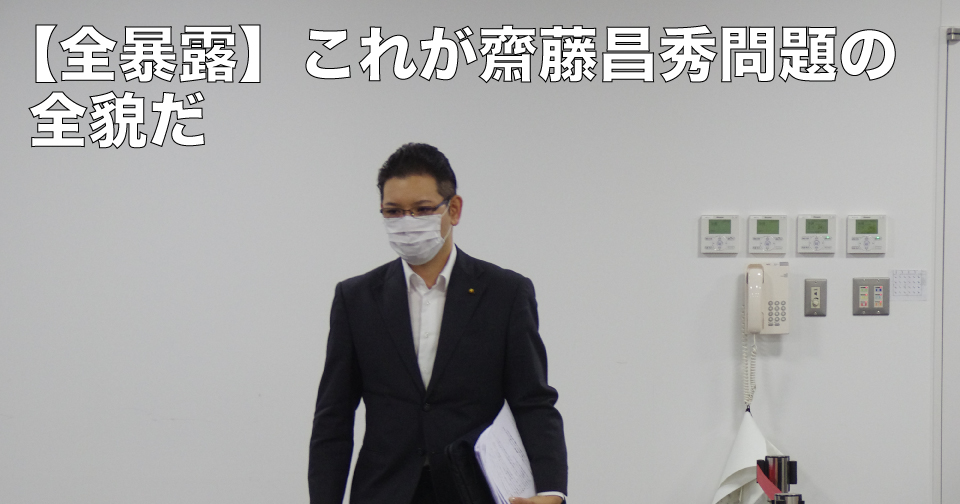「自治基本条例」とは、地方自治体の運営や住民参加の方法などに関する基本的なルールを、地方自治体が独自に策定するものであるとされ、「地方自治の憲法」などと紹介される場合もある。住民の権利や義務、地方議会の運営方針、行政の透明性などが規定され、特に近年では、住民参加を促進し、地方自治をより民主的にしようという目的が強調されている。
住民の意見を反映させ、地域ごとの特色を生かすための手段として自治基本条例が提案されるのは表向きだが、策定される前文や条文には一定のテンプレートのようなものが存在し、その内容については多くの問題を指摘せざるを得ない。
1. 自治基本条例の問題点
(1)「市民」とは誰のことか?
一般的な自治基本条例では「市民の権利と責務、議会と市長等の責務、市政運営の原則などを明らかにし、市民主体の自治の実現を図ること」が目的とされるが、「市民」の定義にはその自治体に居住する本来的な意味の「市民」以外にも、住民登録を持たない通勤・通学者や企業関係者、NPO法人、市民団体や、外国人までもが含まれるケースが非常に多い。例えば、自治基本条例を制定していないA市と制定済みのB市があったとした場合、A市に居住してB市に勤務する人は、A市における「住民」としての権利と、B市における「市民」としての権利を二重に享受できるが、B市に居住してA市に勤務する人の場合は、B市における「市民」の権利しか享受できないという不平等な状態となる。また、B市で設立されたNPO法人などに居住民以外が会員となった場合も、B市における「市民」としての権利を享受できることになるので、特定の思想を持った人々がそのNPOの会員になるだけで、B市においては「市民」として振る舞うことが可能となる。つまりこれらは、自治基本条例を制定しないA市の住民よりも、制定したB市の住民に不利益が生じることを意味している。 同じ千葉県内の浦安市で実際に制定された「浦安市まちづくり基本条例」をみてみよう。
浦安市まちづくり基本条例(抜粋)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内において働き、学び 、又は活動する個人又は団体をいいます。
第4条 まちづくりは、市民の意思に基づいて進められることを基本とします。
3 市及び議会は、市民の行うまちづくりを尊重した上で、市民との協議及び同意を経ることを原則として、市民の信頼に基づいて、その取組を補完し、支援します。
いかがだろうか。市内で何らかの活動をすれば「市民」であるなら、通りすがりの外国人でさえ「市民」。さらに「団体」も「市民」であるなら市内のNPO法人に会員登録した外国人までもが「市民」となり、市政運営にあたってはそれらの「市民」を尊重し、協議して同意を経なければならなくなっている。このことにお気付きの浦安市民の方はどのくらいいるのだろうか。
(2)首長や議会の権限を弱め、地方自治の原則を破壊する可能性
自治基本条例の多くには、「住民投票」や「市民参加」の仕組みが組み込まれている。しかし、これが過剰に機能すると、住民投票による直接民主主義が議会制民主主義を形骸化させる危険性がある。地方議会は、選挙で選ばれた代表が様々な意見を調整し、行政を監視する役割を担っているが、住民投票が頻繁に行われると、そのバランスが崩れ、特定の意見が強調されることになりかねない。さらに、住民投票の実施に関する基準が曖昧な場合、過半数を得た意見が全ての住民の意思を代表しているとは限らないという問題が生じることも考えられる。例えば、ある自治体で住民投票が行われた場合、投票に参加した人の過半数が賛成したとすると、その結果が「全住民の意思」として扱われることになるが、投票に参加しなかった市民は意見を表明していないため、投票結果が必ずしも実際の住民全体の意向を反映したものになるとは限らない。具体的には、都市計画に関する住民投票で、特定の地域の住民だけが参加した場合、その地域の利益が優先される結果となり、他の地域の住民の意向が無視される恐れがある。
また、自治基本条例を「地方自治の憲法」と位置付けた場合、本来法的拘束力を持たない住民投票結果に地方自治体の意思決定が自縛される状況を招くことになる。住民投票は民主主義の一手段に過ぎず、その結果に過度に従うことになれば、首長と地方議会の二元代表による意思決定という地方自治体の原則が機能不全となる危険性がある。
さらに、「市民」に外国人が含まれる場合、外国人にも住民投票権が認められてしまうことから、憲法の「国民主権」の原則との齟齬が生じる可能性がある。日本国憲法では、国民が政治に対して最終的な主権を持つことが定められており、外国人に政治的権利を与えることは、この原則と対立する恐れがある。自治基本条例が「市民」の定義に外国人を含めることで、地域自治における「市民」の権利が拡大し、憲法上の問題を引き起こす可能性がある。
(3)自治体の意思決定がいびつになる懸念
自治基本条例によって「市民」の定義が拡大されることによって、特定の政治団体やNPO、活動家などが条例を利用して地方自治体に影響を及ぼす可能性が指摘されている。国内外を問わず一定の資金力・組織力を持つ組織・団体が、政治的な目的を持って住民投票や市民参加の仕組みを利用し、その意見を強引に反映させることが可能となるため、自治体の政策が地域住民の実際のニーズや意見とは異なるものになる恐れがある。また、市民参加を謳いながらも現実問題としてそこに参加できるのは、平日の日中に市役所の会議室に通えるごく一部の市民に限られるため、特定の価値観や利害関係を持つ少数派の意見が過剰に反映される恐れがある。さらにそれが自治基本条例によって拡大定義された外部の「市民」だった場合、例えば地域の伝統的な行事が、外部市民の「人権」「差別」といった視点で否定されたり、地域にとって重要な開発行為が、外部市民の「環境保全」という視点で中止されるなど、結果的に地域の実情とはかけ離れた政策が推進される懸念もある。
2. 具体的な事例
(1)ニセコ町(北海道)
ニセコ町は、2000年に「ニセコ町まちづくり基本条例」を制定し、自治基本条例の先駆けとなった。この条例は、市民協働を推進し、町民の権利と義務を明確化することを目的とし、「まちづくりに参加する権利」として町民全体の参加を促進している。
しかし、近年のニセコ町の急速な国際化により、外国人住民の増加が顕著となっている。特に、観光業の発展に伴い、外国人労働者や定住外国人が増加し、町の人口構成に大きな変化が生じている。
このような状況下で、ニセコ町の自治基本条例が抱える課題が浮き彫りとなった。特に第10条の2「わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。」と町民の定義を広範囲に拡大していることで、住民登録を有しない外国人や一時的な滞在者までもが町の意思決定に関与する可能性がある点が指摘されている。
また、ニセコ町では国際交流員(CIR)の受け入れや多言語対応の強化など、外国人住民へのサービス向上が進められており、これらの取り組みは、外国人住民の生活支援や文化交流の促進に寄与している。町のリソースや政策に対する外国人住民の期待が高まる一因ともなっているが、「まちづくり基本条例」がこのような政策を推進する根拠となっている可能性が高い。
ニセコ町の自治基本条例が抱える課題は、他の自治体にとっても重要な教訓となっている。特に、外国人住民の増加に伴う自治体運営の変化や、条例の適用範囲とその影響についての議論は、全国の地方自治体にとって避けて通れないテーマではないだろうか。
(2)明石市(兵庫県)
明石市における自治基本条例策定プロセスは、各種団体や市民運動が積極的に関与し、最終的に条例内容に大きな影響を与えた部分があり、外部団体の影響が大きかった事例として注目されている。
明石市は、2006年に「明石市自治基本条例」の制定を目指すため、策定プロセスをスタートさせたが、その過程においては、市民団体やNPOなどの外部団体が重要な役割を果たしている。特に以下のような団体が関与し、それぞれの立場から意見を述べ、条例内容に影響を与えた。
・市民団体の影響
市民団体や市民活動グループは、明石市の自治基本条例策定に積極的に関わり、「市民参加の推進」や「住民の権利拡大」を求め、条例案の内容を強く支持した。特に、「住民参加の権利」を強調し、市民が行政に対して積極的に意見を述べることができる仕組み作りを提案した。なかでも市民が自治体の意思決定に直接関与するための仕組みとして、住民投票や市民協議会の設置を強く主張し、この要求は条例案に反映された。
・環境団体・社会運動団体の関与
環境問題や社会福祉に関する団体の影響も無視できない。これらの団体は、行政の透明性や政策決定過程での市民の影響力を強化することを重視し、自治基本条例が市民の監視機能を強化するものとして機能するよう求めた。
特に、環境団体は「市民の環境に関する意見を反映させる」ことが重要であり、環境保護の観点から行政が市民と積極的に協議する必要性を訴えた。こうした外部団体の意見は、明石市の自治基本条例における「市民参加」の部分に強い影響を与えた。
・労働組合・経済団体の影響
労働組合や経済団体も一定の影響力を持っていた。これらの団体は、自治基本条例の策定過程において、特に「市民の福祉」と「地域経済の活性化」への配慮を求め、地方自治体としての福祉政策や、経済発展に資する施策が反映されるべきだと主張した。
労働組合は、市民の労働環境や雇用の安定についても関与し、これらの問題に対して条例を通じた保障を求めた。一方、経済団体は過度な規制が地域経済に負担をかけることを懸念し、条例案にはバランスの取れた政策が必要だと主張した。
明石市の自治基本条例では、特に、住民参加の仕組みや市民の権利について、外部団体の意見が強く反映される結果となった。しかし、市民参加が促進される一方で、特定の団体が市政に強い影響を与える状況が生じ、公平な意思決定プロセスが損なわれるリスクが指摘されている。
3.千葉県内の状況
現在千葉県内の自治体では、流山市、茂原市、千葉市、浦安市、白子町が、自治基本条例を制定している。
それぞれの条例内容から、懸念点などを指摘しておきたい。
・流山市自治基本条例:2009年
住民基本台帳に記録されている者を「市民」、市民並びに市内で働く者及び就学する者並びに市内の自治会 、NPO及び事業者 を「市民等」と定義し、「市民」が市の主権者であることを明確にし、市民投票に非居住者や外国人、団体を排除している点は評価できるが、それ以外「市民」はすべて「市民等」に内包され、「第11条 市民等は、 市政に参加する権利を有しています。」と「市民等」の権利についても明文化されている。
また、別途定められた市民投票条例では、有権者の6分の1の署名で市民投票の実施を請求できるとしており、首長や議員のリコールを求める場合の3分の1に対して大幅にハードルが低くなっている。
・茂原市まちづくり条例:2016年
市内に住民票を持つ「市民」と「市民等」を別に定義している点は流山市と同様だが、「市民」のみに認められている権利は「まちづくり協議会の設置」のみ。住民投票についてはわずかに「第12条 市は市政に関する重要事項について、市民、議員又は市長の発意に基づき、市民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。」と、発意することが「市民」の権利と確認できるが、住民投票条例は個別の案件ごとに制定するとしており、投票権が「市民等」にまで拡大される懸念がある。
・千葉市市民自治によるまちづくり条例:2020年全部改定
市民投票の定めはなく、ことさら市民の権利を強調するものではないものの、「市民」の定義がされておらず拡大解釈される懸念がある。「市民活動団体の設立、活動の継続と発展のための支援」を市の取り組みと明文化していることから、無用なNPOなどへの補助金交付の根拠となる可能性がある。
・浦安市まちづくり基本条例:2022年
前述した通り「市民」の定義を「市内において働き、学び 、又は活動する個人又は団体」にまで拡大しており、別途定めた市民の市政参加をことさら強調する「浦安市市民参加推進条例」とセットになることで、事実上非住民や外国人、NPOや市民団体・圧力団体にまで浦安市政への積極参加を促すものとなっている。
・白子町まちづくり基本条例:2023年
「町民」の定義がされていない点は千葉市と同様だが、「町民投票」についての定めが「第4条 町民は、町に関わる重要事項について、町民投票の実施を町長及び議会に求める権利を有します。2 町は、町民から請求があった時又は町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができます。」と非常に曖昧で、町民投票が一部の勢力などに恣意的に利用される懸念がある。また、その際「町民」の定義がないことから、非居住者や外国人、団体にまで町民投票権が及ぶ懸念もあり、白子町の人口がわずか1万人であることを鑑みれば、ある程度の組織力を持つ団体がその気になれば投票結果をコントロールすることは比較的容易である。
4.山武市の状況
椎名前市長時代、山武市においても自治基本条例策定を進める動きはあったようだが、議会の同意を得られる見込みがなく、その議論は凍結された状態となっている。「市民自治支援課」という部署名はその名残りであろう。
しかし、自治基本条例の推進者である千葉大学教授関谷昇氏の講演が不定期的に行われるなど、水面下でなおもくすぶり続けている可能性は否定できない。
以前関谷氏の講演に参加した際の内容は、
1.まず「地方都市消滅」というショッキングな話題で、市民の危機感を煽る。
2.次に、人口減で自治体サービスの向上が見込めない中、市民と自治体とNPO法人が「協働」して地域づくりを行う必要があると説く。
3.市民が興味をもつような市民協働による地域づくり事業の実例を幾つか紹介し、市民の関心を高める。
4.そして最後に、市民協働のために自治基本条例の策定が必要であると結ぶ。
というもので、話としては良くできていると感じたが、3で紹介した事例のうちすでに頓挫しているものが含まれていたため、質疑応答の際に、
「なぜ失敗した事例をあたかも成功例のように紹介するのか?」
と質問したところ、
「『失敗することもある』ということを言いたかった。」
と、とても国立大学の教授の言葉とも思えない回答に絶句したことがあった。指摘されていなければ100人を超える参加者はそれを「成功事例」と認識して帰って行く訳なので、このような回答は詭弁以外の何物でもない。我々市民はこのような論法を用いる人物の言説には特に注意を払っていく必要があるのではないだろうか。
関谷氏は現在浦安市の市民参加推進会議の会長も務めている。
5.自治基本条例の思想背景
自治基本条例は、「まちづくり条例」など自治体によってその呼び名は異なるものの、400以上の自治体ですでに制定されている。千葉県内においては54の市町村のうち5市町であるため割合としては1割以下だが、全国的には4分の1近い自治体ですでに制定済みという状況だ。
一時のブームは沈静化したとも言われているが、県下では浦安市、白子町と次々に制定されており、あなたの住む自治体でも突然自治基本条例策定の動きが出てくることも十分予想される。
ここで、なぜ推進者たちが全国の自治体に自治基本条例を制定させようとするのか、その思想背景を考察しておきたい。
(1)グローバリズム志向と多文化共生主義
「市民」の定義が拡大解釈され、外国人や一時的な居住者も参加の権利を持つようになる傾向があるが、これはグローバリズムや多文化共生主義に基づいた思想の影響が強く反映されているものと考えられる。
本来、憲法第15条に基づいて日本国民にのみ与えられるべき参政権が、地方レベルで「市民参加」という名のもとに拡張され、外国人の実質的な政治参加を可能にする動きである可能性が極めて高い。
(2)左派的な市民運動
「市民参加」「協働」「まちづくり」など、一見耳障りのいい言葉で市民の政治参加を推奨、あるいは努力義務としているが、公募メンバーで構成される諮問機関の設置や、自治体の意思決定に市民の住民投票を規定することで、「直接民主主義」の性格を強化して相対的に地方議会の権限を弱め、選挙で選ばれた代表による間接民主主義の原則を形骸化させようとする試みである可能性が高い。
また、環境保護団体、フェミニスト団体、反原発運動など、特定のイデオロギーを持った組織が条例を利用し、地域政策に影響を与えることを目的としている可能性、例えば、環境保護団体が開発計画の見直しを要求するようなケースが考えられる。
(3)公共事業の民間開放を利用した利権拡大
一部の政治家や団体は、自治基本条例の名のもとに、NPOや市民団体への補助金交付を利権の温床として利用するケースも見られる。地方自治体からの資金が特定の団体に集中することで、事実上の利権ネットワークが形成される。特に、行政と癒着した団体が補助金を不正に受給するケースが過去にも多数報告されている。
条例に基づく市民参加制度を特定の団体やグループが独占し、政策決定プロセスが私物化され、政策決定過程を自分たちの都合の良い方向に誘導する可能性がある。
(4) 国家権力の分散と「地方分権」の歪んだ解釈
本来の地方分権は、中央集権を見直し、地域ごとに最適な政策を推進するためのものだが、自治基本条例を推進する一部の勢力は、国家権力を弱体化させるための手段として利用している節がある。かつては「地方自治の憲法」と最高法規性を持たせようとする試みが確認されたが、憲法が最高法規であることは明白であり、近年ではこの表現は見られなくなったものの、依然として市長や議会に自治基本条例遵守を義務付けることで間接的に最高法規性を持たせるようなアプローチは継続されている。
各自治体が最高法規的位置付けの独自のルールを作り、それが乱立すれば、国全体の統一性が失われ、国家としての統治機能が分断される。究極的には幕府の統治が形骸化して各藩が独自ルールで政策決定を行う幕末のような国家体制になるリスクがある。
6.すでに自治基本条例が制定されてしまっていたら
自治基本条例がすでに制定されている自治体に住んでいる場合、以下の点に注意して条例が適切に運用されているかを定期的に確認することが重要ではないだろうか。
(1)内容の透明性を確認する
条例の運用が特定の団体や勢力に偏っていないかをチェックする。特に、市民活動団体やNPO、特定の圧力団体による影響が政策決定に不当に反映されていないかを見極めることが必要。
(2)住民の意見が反映されているかの監視
住民投票や市民協働のプロセスが、実際に公平であるかどうか確認する。特定の意見や団体に政策が偏ることで、自治体本来の公平性が損なわれる可能性がある。
(3)条例の見直しを求める
問題が発覚した場合は、住民は条例の見直しを自治体に求めることができる。自治体に対して、改善要求や住民監査請求を行うことも可能。条例の問題点を指摘し、必要ならば住民投票の条件変更や市民参加の定義見直しを求める。
7. 自治基本条例が未制定の場合の対応策
まだ自治基本条例が制定されていない自治体でも、突然制定の動きが出てくる可能性は十分にある。その際、以下のような対応策を提案しておきたい。
(1)条例案の情報収集と監視
制定の動きが見られた際には、速やかに情報を収集する。自治体が公表するパブリックコメントや意見募集に参加し、条例案の中身を把握することが必要。
(2)住民意見の積極的な表明
市民協働や公聴会などの機会を活用し、自分たちの意見を積極的に述べる。特に、市民の定義や住民投票の条件について、適切な制限が設けられているかを確認することが重要。
(3)地方議会への働きかけ
地方議員に直接意見を伝えることも有効な手段。特に、条例の問題点について議会で議論されるよう働きかけることで、制定前に懸念を払拭することが可能になる。
(4)そもそも論に立ち返る
私たち国民はすでに憲法によって基本的人権を始め、自由権、社会権、参政権、請求的基本権などの諸権利が保証されている。自治基本条例は単に憲法で保証されている権利を平易な言葉で上書きするだけで、一般の住民にとってほぼメリットがない。一方で外国人や非居住者、活動家や圧力団体などは自治体内で住民並みの権利を得られることになるため、そのような条例がそもそも住民にとって必要かという「そもそも論」に立ち返り、条文の逐条議論のフェーズに持ち込ませない。
8. 結論
自治基本条例は、その目的とは裏腹に、住民自治を脅かすリスクを孕んでいる。地方自治をより民主的にするという理念には一定の評価ができるものの、その運用が適切でなければ、地域住民の意思とは異なる方向に進んでしまう可能性がある。すでに制定されている自治体の住民は、条例の影響を十分に監視し、地域の利益が損なわれないよう注意を払うべきである。
また、住民の地方自治参加は、首長や地方議員を4年に一度の選挙で選出する間接民主制度ですでに実現されている。それでも自分が地方行政に参加できていないと感じるのであれば、耳障りの良い自治基本条例に飛びついてこれまで述べてきた様なリスクを甘受するより、選挙の際に候補者の政策をよく精査しているか、しがらみや付き合いで投票先を決めていないか、そもそも選挙に行かないなど、まず自身の政治姿勢を見直す必要もあるのではないだろうか。